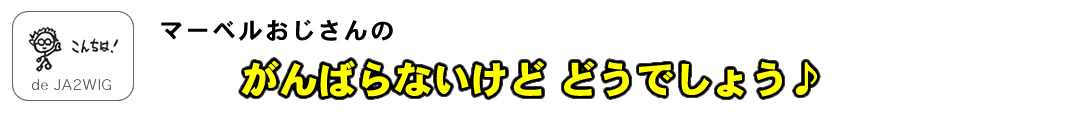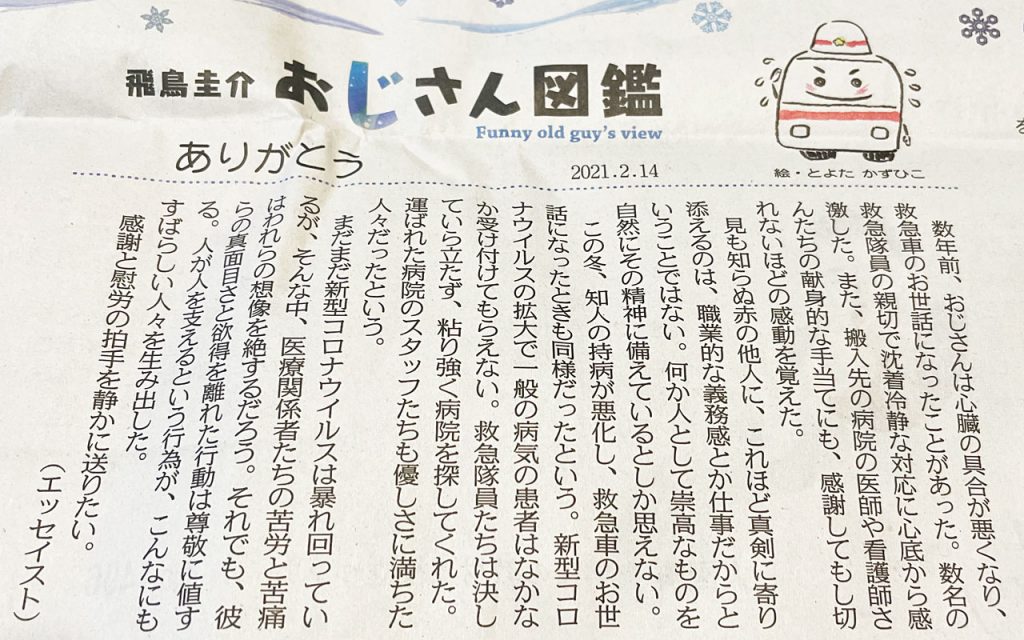中日新聞の日曜版に連載されている「おじさん図鑑」が面白くて毎週必ず読んでいる。飛鳥圭介というおじさんが日頃思うことを辛口で書いているエッセイだ。
例えば、
聞くたびにいらだたしい言葉がある。「ふつうにおいしい」という言葉だ。「ふつうに、とはどういうことだ。ふつうだったらおいしいとはいえないだろう」
そうだそうだ!
英語が国際標準というのは仕方がないことだが、……「ソリューション」「コンプライアンス」「エビデンス」「リボーン」……。なぜ日本語で言えないのか。
そうだそうだ!
こんなふうに最近の風潮を辛口で書いていて、とても共感するのだ。
それでも、ときどきこんないい話も出てきて、嬉しくなる。ぼくも「ありがとう」と言いたい。これは一昨日2月14日(日)に掲載されたものだ。
おじさんが救急車のお世話になったとき、その対応に感動したという話なんだけど、実はぼく自身も過去に2回付き添いで救急車に乗ったことがある。その話をしたい。
一回目はかみさんがある症状で、家のすぐ前にあるかかりつけ医院で診てもらっていた。ところが、ある日さらに具合が悪くなったので、その医院に行くと「これは救急車をすぐ呼びなさい」という。119番に電話すると救急車がすぐに来てくれた。
ぼくは付き添いでいっしょに乗ってから、救急隊員の行動の一部始終を見ることになるのだが、じつに冷静沈着でとても丁寧な対応だった。
そして市民病院の救急外来に着くと、教室2つ分くらいの広い場所に処置ベットが並び、多くの医療機器が備わっていた。すでに数人の患者が処置を受けている。
ストレッチャーが中に入っていくと、救急病棟では受け入れの準備ができていて、専門の医師や看護師のチームらが全員で連携のとれた処置をしてくれた。
そしてチーフと思われる若い女性看護師が、笑顔で優しく対応してくれて、まさに感動的だった。その手際よい行動の全てがじつに頼もしく感じてしまうのだ。
しばらく様子をみるためにカーテンで覆われたベッドで寝ていると、何度もその看護師が来てくれて、どうですか? 気になることはありませんか? と気を遣ってくれた。
待っている間、ぼくは広い救急病棟の隅っこで椅子に座ってじっとしていた。次の救急車が来るまで、その看護師チームがみんな輪になって、チーフの女性がいろんなレクチャーをしていた。まったく休憩をとるということはなかった。
しばらくすると、次の救急車が到着して、また全員がその対応にあたる。ぼくはこの現場をずっと見ていて、これはドラマではない、現実の現場そのものなのだと思いながらも、感動しっぱなしだった。
その後、救急処置のお陰で回復し、数時間後に処方箋をもらい帰宅することができた。
2度目の救急車体験は会社で仕事の最中だった。
現場でいろいろ打合せをしていると、事務の女性が座ったまま全く動かない。様子を見に行くと目をつむったまま下を向いていた。
声を掛けてもまったく反応しないので、これは大変だと思って、すぐに救急車を呼ぶ。しばらくすると、救急車と共に消防車もいっしょに来た。なぜだろう?
駆けつけた救急隊員が声をかけると小さな声で反応した。すぐに救急車に運び応急処置を開始する。すると今度はサイレンが鳴ってドクターカーが到着したのだ。
救急車の中は救急隊員とドクターと看護師が乗り込んできたので、付き添いのぼくは救急車の助手席に3人で乗ることになった。
そして、サイレンを鳴らしながら救急車が市民病院へと向かう間、運転手とその横にいる救急隊員の動きをつぶさに見ることができた。
できるだけ早く、そして無事に病院に着けるように、そしてあらゆる装備を巧みに扱いながら進んでいく。ぼくはその緊張する現場にいるのだ。
その後、病院に到着すると、先ほどと同じように全員が連携して、患者を救うために懸命に働く姿を見ることができた。
今も毎日コロナ患者の対応にあたる病院関係者たちが、懸命に働いてくれているけど、みんなが本当に欲得を離れた行動をしてくれているのだ。
まさに、見も知らずの赤の他人に、これほど真剣に寄り添えるのは、職業的な義務感とか仕事だからということではない。
何か人として崇高なものを、自然にその精神に備えているとしか思えない。そう感じるのだ。医療を支えてくれている人たちに、心から感謝と慰労の拍手を送りたいと思う。